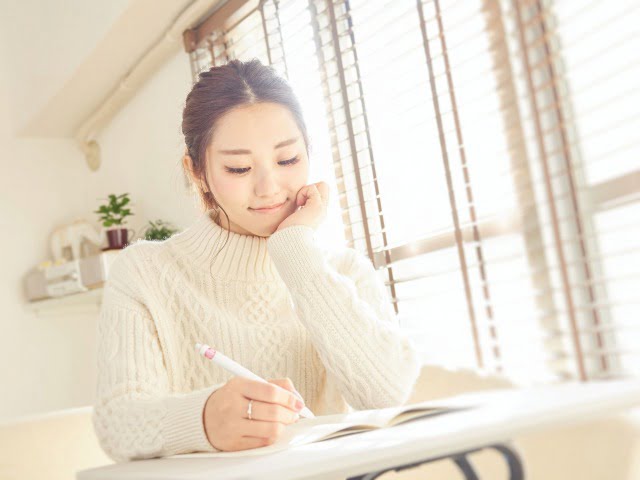そろそろ介護福祉士に挑戦したいけど、実務者研修の費用は高いからどうしようかなぁ…と迷っている方も多いのではないでしょうか?
介護職で長く働くなら、絶対に取っておきたい資格が介護福祉士。給料アップや仕事のスキルアップ、キャリアアップにつながる資格だからです。
介護福祉士になって、もっと待遇の良いところに転職したい…
知識やスキルを高めるために資格を取りたい…
介護福祉士になって職場でキャリアアップしたい…
介護福祉士国家試験の受験資格で必須の実務者研修も、教育訓練給付金制度や貸付制度を利用すれば、費用負担を軽減できます。
ここでは、実務者研修で利用できる専門実践教育訓練給付金や貸付制度をご紹介します。
実務者研修で利用できる専門実践教育訓練給付金
「専門実践教育訓練給付金」は、専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方を支援する教育訓練給付金制度。雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の一般教育訓練給付金に加え、新たに創設されました。
専門実践教育訓練の給付対象講座には、介護福祉士、看護師、美容師などの国家資格取得を目標とする講座が指定されています。
介護福祉士の受験資格である実務者研修においても、支給要件を満たした方が厚生労働大臣指定の講座を受講し修了した場合、支払った受講費用の最大70%が支給されます。
専門実践教育訓練給付
中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した者に対して、公共職業安定所(ハローワーク)から受講に要した費用の最大70%が給付されます。
- 実務者研修の受講費用の50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給
- 受講修了後1年以内に介護福祉士の資格を取得し、就職した場合には受講費用の20%(上限年間16万円)を追加支給
※最長3年間の訓練期間で上限額は168万円(上限年間56万円)
例:三幸福祉カレッジ 厚生労働大臣指定の実務者研修対象者講座
「専門実践教育訓練給付金制度」利用後の実質負担額(税込)
| 保有資格 | 通常受講料 | 50%給付 | 70%給付 |
|---|---|---|---|
| 初任者研修 | 109,670円 | 54,835円 | 32,901円 |
| ヘルパー2級 | 109,670円 | 54,835円 | 32,901円 |
| 無資格の方 | 142,670円 | 71,335円 | 42,801円 |
三幸福祉カレッジの専門実践教育訓練給付金指定講座
- 実務者研修(初任者研修修了者)
- 実務者研修(ヘルパー2級修了者)
- 実務者研修(無資格者)
※実務者研修(介護職員基礎研修修了者・ヘルパー1級修了者)コースは一般教育訓練給付金の指定講座になります。
スクールによって対象講座が異なります。
専門実践教育訓練給付金の支給要件
専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣指定の講座を修了する見込みで受講している方となります。
1.仕事をしている方(雇用保険の被保険者)
- 初めて教育訓練給付金を利用
受講開始日の時点で、被保険者等として雇用された期間が通算2年以上ある方 - 教育訓練給付金を利用したことがある
前回の利用後から受講開始日までに、新たに被保険者等として雇用された期間が通算3年以上ある方
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。
※A社:1年 + B社:2年 = 通算3年
※A社とB社の間に離職期間が1年以上ある場合は通算できません。
2.離職された方(雇用保険の被保険者であった方)
- 初めて教育訓練給付金を利用
離職している期間が1年以内であり、かつ受講開始日の時点で被保険者等として雇用された期間が通算2年以上ある方 - 教育訓練給付金を利用したことがある
離職している期間が1年以内であり、前回の利用後から受講開始日までに、新たに被保険者等として雇用された期間が通算3年以上ある方
※前回利用以前の被保険者だった期間は通算できません。
※離職期間(被保険者でなくなった期間)
※A社:1年 + B社:2年 = 通算3年
※A社とB社の間に離職期間が1年以上ある場合は通算できません。
※派遣社員や契約社員・パートでも、雇用保険に加入していれば対象となります。一方で自営業など雇用保険に入っていない方は、1年以上働いていない方(雇用保険未加入)は対象となりません。
※被保険者等とは、一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者
※受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練講座の所定の開講日、通信制の場合は教材などの発送日です。
対象者かどうかの確認は、自分で判断せず最寄りのハローワークで必ず確認してください。
専門実践教育訓練給付金の利用手順
受講予定日から逆算して、受講開始日の1ヵ月以上前からハローワークでの手続きをスタートします。
受給資格確認
最寄りのハローワークに、自分の受給資格について確認します。
※身分証明書と印鑑が必要です。
事前手続き
受講開始開始日の原則1ヶ月前までに、ハローワークにて「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。
※キャリアコンサルティングは予約が必要です。
このジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を受講開始日の原則1ヶ月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。
ハローワークへの提出書類
- ジョブ・カード
(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの) - 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
(ハローワークやホームページで配布) - 本人住所確認書類(マイナンバーカードか運転免許証など)
※どちらもない方は、住民票の写しと健康保険所の2点でも可 - マイナンバー確認書類(マイナンバーカードか通知カードなど)
- 身元確認書類(マイナンバーカードか運転免許証など)
※どちらもない方は、住民票の写しと健康保険所の2点でも可 - 写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×2.5cm)
※マイナンバーカードの提示で省略可 - 通帳orキャッシュカード
講座申込み
厚生労働大臣指定の対象講座に申込みを行います。
受講料支払い
対象講座のスクールより申込み確認書が届いたら、受講料を本人名義で支払います。
教育訓練給付制度申請手続き申込書提出
「教育訓練給付制度申請手続き申込書」を受講中にスクールに提出します。
受講修了
受講が修了したら、スクールから修了証明書とともに教育訓練給付金支給申請書が送付されます。
1回目支給申請手続
1回目の50%が支給されます
修了証明書発行日の翌日から1ヶ月以内に、ハローワークに必要書類を提出します。
2回目支給申請手続
2回目の20%が追加支給されます
介護福祉士国家試験(原則当年度受験)に合格後、登録日から1ヶ月以内にハローワークに必要書類を提出します。
※被保険者として雇用されていない場合、修了証明書に記載された修了年月日の翌日より1年以内に、被保険者として就業する必要があります。雇用された日の翌日より1ヶ月以内に申請すると2回目が支給されます。
専門実践教育訓練給付金の支給申請期間
専門実践教育訓練給付金の支給申請については、受講開始日から6ヶ月ごとに行う必要があります。6ヶ月以内に受講が修了した場合は、修了日の翌日から1か月が支給申請期間となります。
※専門実践教育訓練給付金の支給申請は、受講経費の総額を6ヶ月ごとに分割した金額で支給申請を行います。
専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類
専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、原則次の5種類です。
- 教育訓練給付金支給申請書(スクールから交付されます)
- 受講証明書または修了証明書(受講証明書については、スクールが定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6ヶ月ごとスクールから交付されます。また、修了証明書は受講を修了した方にスクールから交付されます。)
- 教育訓練給付金受給資格者証(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)
- 領収書(受講者本人が納付した受講経費について、スクールが発行します)
- その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類が必要になります。
※専門実践教育訓練給付金の詳細はハローワークの案内を参照してください。
実務者研修で利用できるそのほかの給付金制度については、別記事の「介護の資格講座で利用できる給付金制度」をご覧ください。
実務者研修で利用できる受講資金貸付制度
各都道府県の社会福祉協議会では、介護福祉士の養成及び確保を図ることを目的に、実務者研修講座を受講していて、修了後に各都道府県の施設で介護福祉士として働く意思のある方を支援するために「介護福祉士修学資金」の貸付けを行っています。
また、介護施設で働きながら介護福祉士の資格取得を目指す方を支援するための「実務者研修受講資金」や、介護職員等として再就職をしようとする方を支援するための「再就職準備金」の貸付けも行っています。
いずれも無利子で、所定の要件を満たした場合には、返還が免除されます。
介護福祉士修学資金
ここでは、山梨県の例を参考にご紹介していきます。
貸付対象者
介護福祉士養成施設に在学し、卒業後に山梨県内で介護福祉士として業務に従事しようとする方
※貸付制度の対象講座の介護福祉士養成施設
貸付限度額
- 修学資金 月額5万円以内(在学期間内)
- 入学準備金 20万円以内
- 就職準備金 20万円以内
- 国家試験受験対策費用 1年度あたり4万円以内
- 生活費加算 生活扶助相当額(※該当者のみ)
全額返還免除となる条件
実務者研修を修了した日から原則として1年以内に、介護福祉士の登録を受けて、山梨県内の介護福祉施設等で継続して5年間、介護業務等に従事した場合には、介護福祉士修学資金の返還が免除されます。
実務者研修受講資金
ここでは、山梨県の例を参考にご紹介していきます。
貸付対象者
介護福祉士養成施設に在学し、卒業後に山梨県内で介護福祉士として業務に従事しようとする方
※貸付制度の対象講座の介護福祉士養成施設
貸付限度額
- 20万円以内
全額返還免除となる条件
実務者研修を修了した日(又は介護等の業務に従事する期間が3年に達した日)から原則1年以内に、介護福祉士の登録を受けて、山梨県内の介護福祉施設等で継続して2年間、介護業務等に従事した場合には、実務者研修受講資金の返還が免除されます。
再就職準備金
ここでは、山梨県の例を参考にご紹介していきます。
貸付対象者
介護職員等(介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者等の有資格者に限る)として1年間以上の実務経験を有する離職者で、山梨県内において介護職員等として再就職しようとする方
貸付限度額
- 20万円以内
全額返還免除となる条件
山梨県内において介護職員等として再就職した日から継続して2年間、介護職員等の業務に従事した場合は、再就職準備金の返還が免除されます。
申請から貸付・返還免除までの流れ
実務者研修の講座があるスクールに入校
事前に貸付金制度が利用できるかを必ず確認してください。
社会福祉協議会で申請書などの必要書類の審査
基本書類の他に以下の連帯保証人関係書類、法定代理人関係書類が必要になります。
申請に必要な書類
- 基本書類
借受申請書
住民票の写し
印鑑登録証明書
介護施設・事業所の推薦書
実務者研修受講証明書
個人情報の取扱に関する同意書 - 連帯保証人関係書類
住民票の写し(本人:本籍地の記載があるもの)
印鑑登録証明書
収入及び課税状況が確認できる書類 - 法定代理人(親権者または後見人)関係書類
印鑑登録証明書
貸付決定の通知後、契約書を社会福祉協議会に提出します。
受講資金が振り込まれます。社会福祉協議会に借用証書を提出します。
実務者研修修了後に、修了証明書を社会福祉協議会に提出。介護福祉士国家試験に合格後、介護福祉士として登録して介護業務に2年間従事。
次年度までに介護福祉士国家試験に合格しないと全額返済(無利子)となります。
免除申請後に、社会福祉協議会より借用書が返還されます。
まとめ
実務者研修の受講料は保有資格によって異なりますが、ヘルパー2級・初任者研修を取得している方でも平均10万円〜15万円がかります。
一定の要件を満たせば受講料負担を軽減できる専門実践教育訓練給付金や全額返還される貸付制度を利用して介護福祉士を目指しましょう。
しかし働きながら実務者研修を修了し、介護福祉士国家試験に合格するのは費用負担だけでなく時間もかかるので大変なことです。
働きながら介護福祉士の資格取得目指している方にはかいご畑のキャリアアップ応援制度がおすすめです。
全国の実務者研修スクール一覧